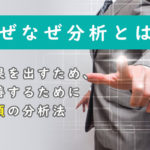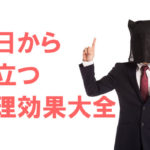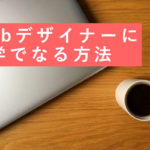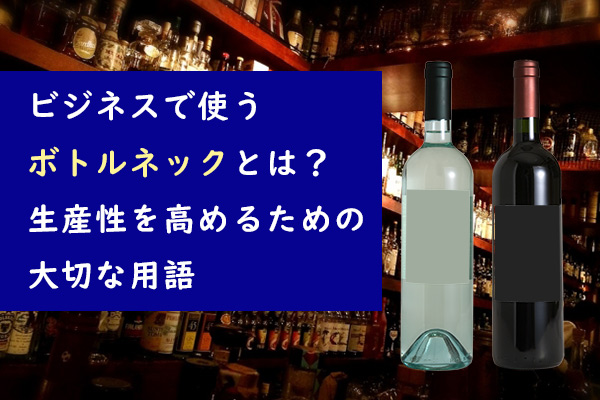

・ボトルネックってよく聞くけど分からない。
このように「ボトルネック」をビジネスシーンで聞いたことはあるけど、分からないという方にしっかり理解いただけるようにご紹介します。
ボトルネックは、個人・部署・会社問わず、生産性を上げるために重要な知識です。
ボトルネックとは?

ボトルネックとは、作業工程の中で一番処理能力が低い箇所の事を指すビジネス用語です。
ビジネス用語とは別に本来の「ボトルネック」とは、ワインボトルなど瓶の先端の細い部分の事を指します。
ワインも、ボトルネック(先端の部分が細くなること)によって口から出る液体の量が制限されます。
ビジネスシーンの例では、社員の資料作りが速くても「上司の確認待ち」によって仕事がストップしてしまっているような場合。
これは「上司の確認」がボトルネックの作業になっています。
逆に上司は確認が来るのを待っていて、社員の資料作りが遅い場合は、「社員の資料作り」がボトルネックです。
生産性を上げるためには、ボトルネックを見つけ、意識し、改善することが重要です。
作業の時間はボトルネックで決まる。小学校の集団登校の例
小学校で高学年から低学年まで一緒に登校する、集団登校をしたことはあると思います。
この時、集団全員が学校まで付く登校にかかる時間は、歩くのが一番遅い人によって決まります。
歩くのが遅い低学年を残して、走って学校まで行くとします。低学年の子は残されて途中で寄り道したり迷ったりしてしまうと、この集団全員が登校する時間は大幅に遅れます。
一方で、歩くのが遅い低学年を真ん中にして、休んだり遊んだりしないよう上級生が囲んであげると低学年の速度で歩くことになりますが、ロスが少なくなり結果的に早く着くことが出来ます。

このように、作業で生産性を上げるためには、一番遅い部分「ボトルネック」を改善しつつ、合わせていく事も必要です。
マーケティングやサービスにおいてもボトルネックは考えられる
ボトルネックは、生産する時に効率の悪い部分ですが、マーケティング・サービスにおいてもボトルネックはあります。
Webサイトの例
ネット通販などは、「広告を見る→商品を見る→カートに入れる→購入手続き」といった一連の動作があります。
商品を見る部分が、使いづらく分かりづらい=ボトルネックになっている場合、顧客満足度の低下や、離脱なども考えられます。
遊園地など娯楽施設でもボトルネックが
私の大好きな東京ディズニーランドもボトルネックがあります。それは入場時です。
開園30分前に入り口に並んだとしても、手荷物検査や入り口での詰まりにより、開園30分後に入園なんてこともあります。
これは完全にボトルネックと言えます。ボトルネックを解消するためオリエンタルランドは、入り口の改修工事を行っています。
他にも、スーパーではレジ待ち。飲食店では注文してから食事が運ばれるまでの調理時間がボトルネックになっていたりします。
特に飲食店のボトルネックは、1日にさばける顧客の数が決まってくるため、売上にも大きく影響します。
ボトルネックの3つ原因
ボトルネックは、工程のなかで一番遅い部分なので、どんな作業においても必ずあります。
その中には大きく3つの原因が考えられます。
- 技術的なボトルネック
- 精神的なボトルネック
- 仕組み的なボトルネック
技術的なボトルネック
新人プログラマーがプログラミングする場合は、技術的に劣るためボトルネックとなります。
また、適材適所ではない人員配置などを行うと、その作業が苦手なのに行うというケースになってしまいボトルネックになります。
研修などで技術力アップや、人員配置、最新テクノロジーを入れるなどで技術的なボトルネックを解消することが大切です。
ただし、忘れてはならないのはどんな作業にも、スピードアップの限界があります。
例えば病院では「診察」がボトルネックであるケースがほとんどです。
診察は重要な部分なので、安易にスピードアップは危険です。
無理なスピードアップ・根性論のスピードアップなどはしないようにしましょう。
精神的なボトルネック
機械やシステムではなく人力で行っている作業がボトルネックになっている場合は、人の精神・体力が問題の場合もあります。
例えば、ミスに非常に厳しい上司がいると、部下がビクビクしてしまいミスしないように過剰な確認が入ってしまい作業が遅くなっている。
あるいは、士気が低下し作業効率が低下しているという事も考えられます。
昨今リモートワークが一般化しつつあります。子供が家にいる環境でのリモートワークの人は、子育ての影響で仕事に集中できないという人もいるでしょう。
これもボトルネックの原因ですが、なかなか難しい問題です。
人の精神状況や、環境・体力などの問題にも寄り添って改善していく事も大切です。
仕組み的にスピードアップが出来ない
成果物が出来たら上司に紙にハンコを押してもらわなければいけないという場合。
上司が忙しくて探す時間、ハンコが無かったら取りに行く時間など仕組み的にスピードアップできない場合です。
おおよその仕組みは、IT・デジタルを駆使すれば改善が出来るでしょう。
生産性を上げるツールの展示会などに参加して情報収集することも良いでしょう。
また、実はボトルネックの作業はいらないという場合もあります。仕組みそのものをなくす・改善するという方法も考えられます。
ボトルネックとTOC理論
TOC(Theory of Constraints)理論とは、「制約条件の理論」と言われ、イスラエルの物理学者エリヤフ・ゴールドラット氏が考案しました。
「ザ・ゴール」と呼ばれるビジネス書にて紹介されて有名になっています。
TOC理論では、ボトルネックをしっかり管理し改善することで生産性を上げる事ができます。
TOC理論は、PDCAのように、3つのステップを循環させて使う方法です。
- ボトルネックはどこにあるか見つける
- ボトルネックを改善・効率を最大化する
- ボトルネックに全体を合わせる
- 新たなボトルネックを見つけ、改善する(1~3)を繰り返す
ボトルネックはどこにあるか見つける
「仕事で確認待ち」がボトルネックであれば、見つけることは簡単です。
しかし、ライン生産など製造工場において、工程が多い場合があり見つける事が難しくなります。
下記のようなポイントで見つけていきます。
- 作業の遊び時間・待ち時間のある工程の1つ前はどこか
- 作業が詰まっている部分はどこか
ボトルネックを改善・効率を最大化する
ボトルネックが見つかったら、それを改善すれば全体の生産性が上がります。
なぜ、そこだけが他と比べて作業効率が悪いのかを確認し改善していきます。
例えばスーパーでレジ待ちが長いといった場合、レジの効率を上げるために社員スキルを上げる。レジの台数を増やす。レジスターを最新のものにするなどが考えられます。
ただし、大切なのはボトルネックを改善する時は、原因をしっかり特定することです。
「レジが遅いから社員のせいだ」となってしまっては、社員も疲弊しますし既にハイクオリティーを出していたら物理的に無理でしょう。
釣銭を手作業でやっているから遅いなら、自動で釣銭が出るレジに変える。
バーコードの読み取りが悪い場合は、読み取り機を修理・改善するかバーコードを工夫する等も考えられます。
これらは「なぜなぜ分析」にて分析しましょう。下記にて紹介しています。
-

【なぜなぜ分析とは?】結果を出す・改善するために、必須の分析法
仕事で、改善すべき点が分からない。 改善しているのにちっともよくならない。 そんな方に対して、自動車メーカーで有名なトヨタ車が提唱した「なぜなぜ分析」について解説していきます。 人の暮らしを改善して良 ...
続きを見る
ボトルネックに全体を合わせる
ボトルネックは、改善しても限界がある場合があります。
レジもどんなに改善しても、圧倒的に早くなるには今の技術では限界があるでしょう。
そんな時は、レジ待ちによって顧客の満足度低下を避けるため、そもそも顧客を減らすという事も考えられます。
小学校の集団登校の例のように、ボトルネックのスピードに全体のスピードを合わせるという事です。
例えば、混雑以外に来た場合は、ポイント2倍などお得になる施策を出す等考えられます。
工場においても、ボトルネックの改善の余地が難しければ、周りの工程をボトルネックの作業に合わせた量にすることが最適です。
無理にボトルネックを100%以上の稼働にしてしまうと、機会であっても故障やトラブルの原因になります。人であっても精神的な疲労が出てきてしまいます。
新たなボトルネックを改善する
見つけられた作業のボトルネックが解消できたとしたら、他に必ず工程の中で一番生産効率の悪い作業が出てきます。
仮にレジの効率が上がったとしたら、レジの後の袋詰めで行列が発生することが考えられます。
新たに現れるボトルネックを見つけ1~3を繰り返していきます。
こうすることによって、生産性は少しずつ高められていきます。
さいごに
ボトルネックは、改善することで生産性を上げられます。
しかし、限度があります。低学年の子を高学年と同じスピードで走らせることは無理です。
低学年の子が遊んだり寄り道しないようにしながら、スピードを合わせる事こそが生産性を上げる方法です。
是非、ボトルネックを改善して生産性を上げていきましょう。