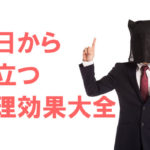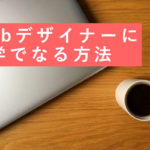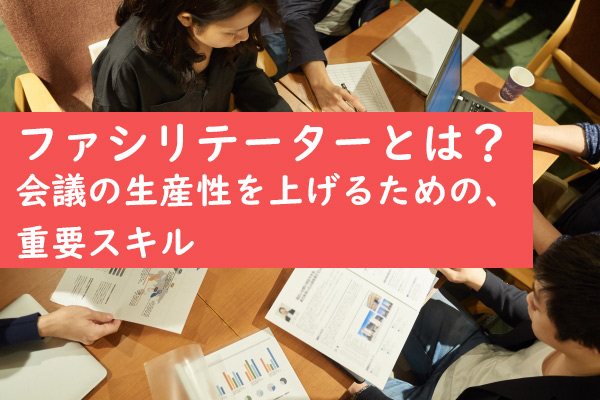

・意見が言えない
・ダラダラ会議が続く
こんな状況が起きる場合は、ファシリテーターの役割が重要になります。
会議などグループや組織で、様々な意見を吸い上げ中立的な立場で物事を進めていく人の事をファシリテーターと呼びます。
主にビジネスでのファシリテーターは会議において求められます。
会議の進行役とも言えますが、ファシリテーターは、定義の通り中立的な立場で進めていく事が求められます。
ビジネスの会議では地位の高い人などが進行役となり、周りが発言し辛い状況になるケースや、強引に物事が進めてしまうケースなどはないでしょうか。
反対に、進行役が適切に進行せず、議題から脱線したまま戻ってこず、長時間の会議になるというケースもあるかもしれません。
このような状況にならない為に必要なのがファシリテーターです。
考え方とコツを掴めば、ファシリテーターとして会議を円滑に進める事が出来ると思います。
また、進行役でなくても、ファシリテーターの概念を知っておく事で、会議における自分の役割が見えてくるかもしれません。
ファシリテーターとは?
ファシリテーションをする人なので、ファシリテーターと呼びます。
ファシリテート(facilitate)は、「容易にする」「促進する」という意味です。
つまり、物事において円滑に進める人と言えます。
プロジェクトを進める時においてもファシリテートは大事ですが、ビジネスにおいては「会議」にて使われることが多いです。
会議は、時間内に議題に対して意見を交えたうえで、最適な決定を行うものです。
報告会議もありますが、情報を共有して問題はないか意見を交えて確認し合うという場です。
これらを実現させるための、会議の進行役がファシリテーターです。
ファシリテーターが、会議で行うべき事
意見の吸い上げを行う
会議で良い決定を行うためには、様々な意見をしっかり吸い上げる事が大事です。
会議では、新入社員や話すのが苦手な人は、発言をしない傾向にあります。
大抵、発言をしていない人は冷静に物事を見ている事が多く、出ている意見とは違う意見を持っていたりします。
そして、後々重要な事に繋がる可能性もあります。
新規事業の立ち上げ会議などは、やってみなければわからない事が多く、楽しい会議でもあります。
そのため、「これはいける!」「きっと大丈夫!」といったイケイケムードになる事もあります。
否定的な意見を言うのは空気が読めない人のような状況となり、失敗した時のリスク・案の根本的な欠陥を確認しないまま物事が進んでしまう可能性があります。
そして、あとあと「あの時こうだとおもったのだよね」と蒸し返すような意見が出るケースがあります。
同じような経験をした方は多いのではないでしょうか。
「早くいってよ」と思いたくなる部分ですが、実は言い出し辛かった状況がいけないのかもしれません。
会議では、このような重要な意見を逃さない為に、参加者の様々な意見を吸い上げる必要があります。
○○さんの意見はどうですか?と意見を言っていない人に対して聞いて見る事や、そもそも全員が意見を言いやすい楽しい雰囲気を作り出すという事も大切です。
様々な視点でとらえ議論を加速させる
意見を言いやすい場・雰囲気を作り出す場合には、意見が出やすい状態に持っていく事が大切です。
その為には、意見を様々な視点で捉え新たな質問・論点を生み出す事です。
例えば、「新規事業はやるべきではない!」と意見が出てきた場合は、1つの意見として捉えるのではなく、「どうしてやるべきではないのですか?」と深掘りして質問してみましょう。
他にも「もし新規事業をやらなかった場合のリスクはどうでしょうか?」など、色んな視点で質問を投げかけてみます。これは、意見を上げた人に聞くだけでなく、参加者全員に考えてもらいます。
このように、1つの意見から反対の視点などで、疑問を投げかけ議論を加速させます。
こうする事により、意見は出やすくなり議論が進みます。
議論を加速させるための質問
- 意見の通りの決定をした場合のリスクはどうか?
- なぜ、そう思うのか?
- その意見は、どうしたらよくなるのか?
- もし、○○の立場であった場合はどうでしょうか?
意見をまとめる
会議の中では、せっかく意見をしてもらっても「何を言いたいのか、分からない」「言いたいことがまとまっていない」という場合もあります。
意見をまとめてから話して!と言ってしまうと意見は出なくなります。
その為、意見が出たら、その意見の意図をまとめながら聞きく事が大切です。
- つまり、○○ということですね?
- 〇〇さんの意見と、同じ(反対)という事ですね?
というような、質問を投げかけて参加者全員が同じ認識になるようにするのがコツです。
また、専門用語や分かりづらい単語が出てきた場合は、質問したり代わりに解説するという事も大切です。
会議の流れの極端化を防ぐ
会議では、場の空気感で極端に議論が傾きやすくなります。
- みんな同じ意見だから間違いない
- みんなのやる気が上がってきたから大丈夫
といった前向きの極端から、全員が決定を回避したい、反対といった意見で埋め尽くされる場合もあります。
こういった会議の流れが極端に傾いた時こそ、ファシリテーターの出番です。
ファシリテーター自ら、「空気の読めない人」と言われるような意見を投げかけてみる事です。
例えば以下のような感じです
「皆さん、この案で新規事業を始める方向で進める流れになっていますが、もし失敗したとしたらどんな要因があるでしょうか? また、〇〇の点は大丈夫でしょうか?」
もし、「大丈夫大丈夫!」など感情論・抽象的な意見しか出ない場合は要注意です。
もう少し議論を重ね慎重に進める必要があります。
色んな視点の意見を吸い上げる事が大切とお伝えしましたが、もし色んな視点の意見が出ない場合はファシリテーター自ら違う視点で投げかけましょう。
話の脱線やダラダラ時間を防ぎ、タイムキープを行う
会議は、盛り上がった方が良いですが、盛り上がると話が脱線していきます。
「そういえば、〇〇の話はどうなったの?」と言ったように異なる議論になってみたり、10人近く参加しているのに、1対1のやり取りが始まってしまったりします。
議題以外の話も重要かもしれませんが、会議が長引く原因になります。
別途会議を設けるか、必要なメンバーで別途話し合ってもらう事が大切です。
ファシリテーターは、「今回の議題とは少しそれてしまったので、元に戻しましょう」のように話題の脱線を阻止していきます。
物凄く厳格に脱線を阻止してしまうと、良い意見が出なくなってしまうので、少し会話してもらったのち本当に関係なければ戻すとよいでしょう。
ファシリテーターの注意点
ファシリテーターの中立性を忘れない事
極端に話が傾いてしまうようなときは、ファシリテーターも同じ意見になっている場合があります。
個人の考えではあっているかもしれませんが、ファシリテーターの役目としては、様々な視点で捉え中立的な立場にいる事です。
回りの意見に左右されないように注意しましょう。
先入観をなくす
社内の会議であれば、ファシリテーターも社員です。
普通に会議に参加していると先入観にとらわれてしまいます。
繰り返しですが、ファシリテーターは中立的な立場なので、先入観を捨てましょう。
特に、会議では「誰がいったから」という要素が大きくなりがちです。
先入観を捨てるためには「人と意見を分ける」という事が大切です。
嫌いな人の意見だと、すべての意見が悪く思え、反対したくなるという事もあるでしょう。
反対に、好きな人・信頼している人の意見は、すべて良いものだと思う事もあるでしょう。
しかし、人は嫌いだとしても意見まで悪いかどうかは分かりません。
信頼できる人であっても、すべてが良い意見である保証はありません。
意見は誰が言ったかが重要ではなく、意見自体が重要なため、意見自体に目を向けて考えましょう。
ファシリテータースキルを高めるためには?
テレビ番組などの司会者を研究する
ニュース番組などでは、時間が守られている為、様々な人のコメントを紹介しつつも時間内に終わらせます。
また、専門家の意見などは、質問を投げかける事で分かりやすくしています。
出演者くまなく意見を聞いていくという事もあります。
テレビの司会者は、ファシリテーターの鏡とも言えます。是非研究してみましょう。
行動心理・心理効果を覚える
ファシリテーターは先入観にとらわれてはいけません。
その為には、自分の心の動き・考え方の動きを理解する事が大切です。
先入観に関しては、行動心理学などで様々な法則があります。
これらは、知って考える時に思い出せるようになるだけで、先入観を少なくする事が出来ます。
下記にて紹介していますので、是非確認していましょう。
-

【保存版】明日から仕事に役立つ行動・認知心理効果用語集
「見ちゃダメ」といわれると見たくなってしまいますよね。 人間の行動には「つい」考えてしまう・やってしまう事があります。 今回はそれらの効果を一覧にまとめました。 使用用途としては主に2種類あります。 ...
続きを見る
最後に
ファシリテーターは定義としては簡単ですが、実際に完璧に進める事は非常に難しいです。
私も、会議の進行役である事が非常に多いです。
ファシリテーターについて紹介しましたが、常に失敗と反省の繰り返しです。
ですが、意識する事によりファシリテート能力は上がっていきます。
是非、意識して良いファシリテーターになりましょう。