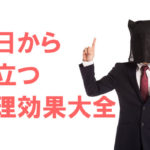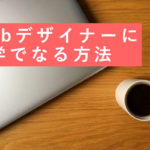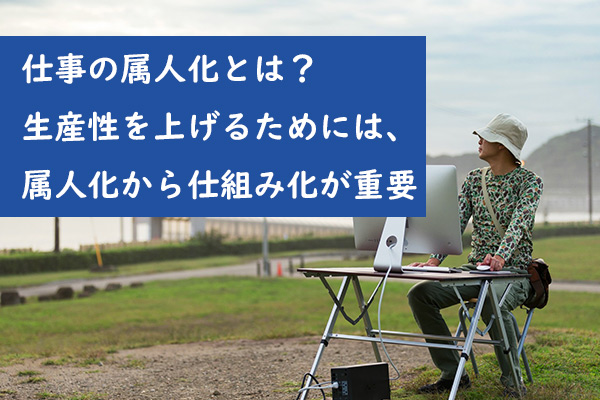

・あの人が辞めたら終わる
・あの仕事はどうなっているか分からない
このように、仕事が誰か1人に依存している事を属人化と呼びます。
属人化していると、今日・明日のタスクにおいてはメリットが多い物の、長期的にみるとかなりデメリットが多く、企業としての大きなリスクを抱える可能性もあります。
今回はそんな、仕事の属人化について紹介したのち、仕組み化する方法をご紹介します。
仕事の属人化とは?
「あの人にしかできない」といった、1人に依存した仕事の事を属人化と呼びます。
反対に、コンビニの定員などのように、学生である高校生でも一人前に仕事が出来るものは、仕組み化された仕事と言えます。
働き手にしてみると、属人化した仕事は希少性の高い仕事になるため、待遇がアップしやすいという一面があります。しかし、企業から見てみると、その人がいないと仕事が回らないという事になってしまいます。
個人事業主や、数名程度しかいない企業であれば仕方のない事ですが、一定レベルの企業の場合や、ビジネスを拡大していくには、脱属人化が必要です。
これは、会社の経営の立場の問題に見えますが、1チームだとしても同じです。リーダーしかできないではなく、リーダーが休んでも誰でも変わりが務まる状況が好ましいです。
※医師、弁護士など高度な仕事の場合は、属人化から離れることが出来ないケースもあります。その代わり、その仕事に就くためには大変な労力がかかります。
反対の仕組み化とは?
属人化の反対には、仕組み化という言葉を使われる事が多いです。
仕組み化とは、誰が行っても一定のレベルで作業が出来るものです。
先ほどお伝えした通り、コンビニの定員は、高校生など未経験でも短期的に一人前に働く事が出来ます。チェーン店の飲食店などでは、どの店舗でも料理の味が変わることはほとんどなく、均一の水準でサービス提供が出来ています。
これには、人に頼るのではなく、仕組み作りを徹底した事によるものです。 仕組み化が出来た企業の多くは、事業拡大が出来ています。
属人化がもたらすデメリット
さて、自社の事業は、属人化しているのか?判別が難しい事もあると思います。
デメリットを1つずつ紹介していきますが、もし当てはまる状態であれば、その仕事は属人化しているかもしれません。
ブラックボックス化し、状況が見えなくなる
属人化して、その人にしか仕事ができないという事は、その人しか状況が分かっていないという事です。
例えば、プログラムが分かる人が1人しかいないとして、セキュリティー上好ましくないプログラムの記述があっても、周りの人は気づく事が出来ません。
担当者であるプログラマーも気づくことが出来なければ、最悪個人情報の漏洩等、大きな被害を生む事になるかもしれません。
プログラマーの例は、極端だとしても、営業が1人であれば、顧客とのやり取りの状況が見えないという事もあります。広告担当が1人であれば、実は効果のない広告を出していた。相場より高い広告費をかけてしまっていたという事もあり得ます。
既に、あの業務はどうなっているか全然わからないといった、ブラックボックス化された業務があるとしたら属人化状態になっているかもしれません。
最低でも2人以上、理想は誰が見ても状況が分かり、異常か正常か分かる状態が好ましいですね。
離職した時のリスクが高く、不要な気遣いが発生する
属人化している業務は、その人が離職した時に誰もできなくなるという事です。
特に専門性が高い場合は、「なんとかなる」可能性は低く、辞めさせない努力が重要になります。
そうなると、強いことは言えない、ある程度の業務に対する悪い態度も目をつぶるようになってしまいます。
どんな仕事においても、利益を高めるために貢献しなければなりません。
その為には、どんな人でも改善が必要ですし、頑張らなければならない事があります。お互い指摘し合い切磋琢磨するという事も大切になります。 しかし、強く言えないという事は、その業務の改善が見込めないという事にもつながってしまいます。
個人的なやり方で、仕事のレベルアップができない
前項で紹介した事とつながりますが、属人化した業務を担当する人のレベル=その仕事のレベルになってしまいます。
本人に向上心があり、良く勉強し、成長している状態であれば問題ありません。
しかし、属人化した業務の場合、その人の地位・権限が強くなり快適な立場になってしまうと、努力を怠るという場合も考えられます。
さらに、努力が出来ていたとしても、自らの仕事を客観的に評価できる人もいない場合、成長が出来ないという事も考えられます。
その為、個人の成長=その仕事の成長につながるため、仕事のレベルアップが出来ない可能性があります。
事業の拡大化がし辛くなる
属人化の反対である仕組み化が出来るという事は、誰でも出来る仕事という事です。
つまり、企業目線でいうと、安い人件費で獲得できる余地が高くなります。
例えば、営業も台本通りに読めば獲得できるという場合は、台本を読むことが出来る人ならば誰でも出来るという事です。
その為、人材募集をするときにも集まりやすくなります。またすぐ即戦力にすることが出来ます。
しかし、属人化になっていると、その仕事を出来る人を採用するのが難しくなります。
また採用できたとしても教育する時間・コストがかかってしまいます。
その為、一気に人材を増やして事業を拡大することが難しくなります。
属人化にもメリットはある
属人化のデメリットを多くお伝えしました。確かに、仕組み化が可能であれば、仕組み化をした方が良いですが、出来ないという企業も多いと思います。
それは、メリットもあるからです。
高いクオリティ、品質の維持が出来る可能性がある
そもそも属人化作業とは、士業やコンサルタントなど、専門性のスキルが高い場合に見られる事です。
高い知識・経験などが必要なため、出来る人が少ない状態です。 その為、属人化しているという事は、社内においては専門性が高く誰でも出来る状態ではない為、適材適所で出来る人に任せた方が高い仕事のクオリティを維持できる可能性があります。
今日、明日で行う時は属人化の方が早い
属人化を脱出するためには、人員を増やしたり仕組み化をしなければなりません。
その為には、1次的には売上にはつながらない管理業務が増えてしまいます。
仕事が忙しい時に、こういった作業を行う事はリスクも伴います。
マニュアルなどを作り、新たな人材を採用した場合、マニュアル以上の事を直ぐに求めることはできません。まずはマニュアルに慣れてから、品質の維持が出来るようになっていきます。 それを教育している時間・余裕があればよいですが、ない場合は既にプロフェッショナルの人に仕事をお願いした方が、早く確実な仕事をしてもらえる可能性が高いです。
属人化を脱出するためには?

属人化状態の問題意識を担当者含め全員が持つ
最初に行う事は、属人化という状態が、企業にとっても現担当者にとっても良くないという問題意識を持つことが重要です。
当記事を読んで頂いている方は、企業にとって良くないという事は理解しているとおもいます。
ただし、属人化状態を脱出するためには、担当者の立場からみても問題だという事を認識してもらわなければなりません。
担当者の立場から見ても、属人化は忙しい時に仕事が集中してしまう。チームをマネジメントするようなスキルアップは目指せない。ずっと最前線で働き続けなければいけないなどデメリットは多くあります。
担当者にも認識してもらえるよう、丁寧な話し合いをしましょう。高圧的にではなく、互いに心底理解することが大切です。
属人化を脱出するための仕組み化をする
属人化を脱出するための一番の理想が「仕組み化」です。
誰でも出来るようにマニュアルの整備、ミスが起きない仕組みを整えるという事です。
例えば、検品作業で長年の経験から見極められる作業などがあるとします。
仕組み化するという事は、「○○の時は不合格、それ以外は合格とする」といった定義を明確にしたり、AIなどのツールを導入し、人間は不合格になったものを取り除くだけで良いという仕事にしたりします。
また、経験者ではないとミスが起こるような作業は、ダブルチェックをするなどミスが起きにくい方法、出来ればミスが起きない方法を検討することが大切です。
これらを整えていくためには、ミスが起きた時に絶対に人のせいにはせず、仕組みを改善するという事が大切です。
同じ専門知識を持つ人材を増やす
プログラマーなどの場合、マニュアルを整備したところで根本のプログラミングスキルは身に付けられません。
そういった作業は、同じ専門知識を持つ人材を増やすことが重要です。
人材を増やすという事は、コストも多くかかりますが、属人化によるデメリットが解消されるという観点で考えた場合、結果的には費用対効果が非常に高い事かもしれません。
ただし、専門知識を持つ人材の場合は、募集すること自体が難しい場合もあります。
また、属人化の作業の担当者が、自分の立場を守るために自分より出来ない人を採用したり、採用自体を否定する可能性もあります。
採用するにも一定の知識が必要になりますので、長期的な観点での対策が必要です。
多少の品質低下、リスクは妥協する
属人化をやめ、仕組み化をしようとするときに、定番として出る発言があります。
- 今より質が落ちますがよいでしょうか?
- 今より〇〇が悪くなりますがよいでしょうか?
これは属人化のメリットでもふれたように、確かに仕組み化して出来る人を増やすようにするという事は、仕事の質を下げるという事です。
しかし、これを妥協しないといつまでたっても仕組み化はできず、長期的にはデメリットが大きくなってしまいます。
その仕事の本当に重要な部分・根幹の部分が弱体化するのであれば、慎重になった方が良いですが、妥協できるリスクであれば、1次的に目をつぶってでも仕組み化を優先しましょう。
さいごに
属人化というものは、状況としてあまり良くない反面、それぞれ働く側の立場から見ると属人化している方が安心であるため、仕組み化するには人間関係・信頼関係が重要になります。
複雑な状況が絡み合いますが、仕組み化出来ると結果的には良い環境を作ることができるかもしれません。 是非脱属人化を目指し「仕組み化」を目指してみてください。