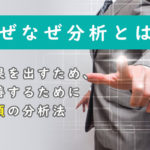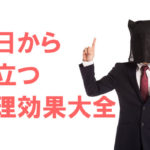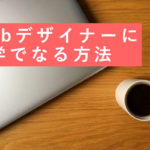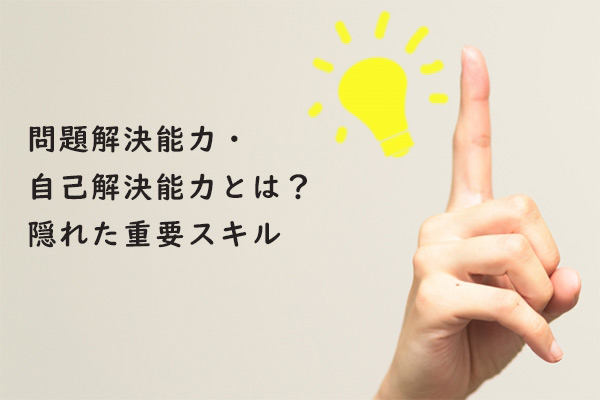
今回は自分で物事を解決する自己解決能力の重要性、鍛え方をご紹介します。
さて仕事で、分からない事があった時どうしますか?
大きくは二つに分かれると思います。
- 自分で考え調べ、自己解決しようとする
- 同僚・先輩に教えてもらう
どちらが良いというわけではありません。自分で解決する事も重要ですが、ミスの許されない事や重要な事・調べても分からない事や、おそらく調べても分からないであろう事は、早めに同僚・先輩に教えてもらう事も大切です。
結論、短期的な仕事の進め方はケースバイケースです。しかし、ビジネススキルとして長期的な視点を見た時は自己解決能力を高める事が非常に重要です。
なぜなら、仕事が高度になる・先輩になるにつれ教えてもらえる事が少なくなるからです。
極端ですが、社長はコンサルなどでアドバイスを聞く事はありますが、経営に対して手取り足取り教えてもらうという事はありません。
自分の力で考え、答えを見つけ、その責任を自分で負うのです。
社長でなくてもリーダーなど誰かを引っ張っていく立場になると、多かれ少なかれ自分で調べ・考え解決する事が求められます。
反対に、自己解決能力が低い人は、マニュアル業務人間となってしまい、出世しても活躍する事は厳しくなります。
因みに、某IT会社のプログラマー採用での重要な指標の一つに、「自己解決能力」を上げていました。
プログラミングのレベルが今高いか低いより、今後自分で成長していけるのかどうかが問われるようです。
自己解決能力が低い人の特徴
そもそも、自己解決能力が高い人、低い人とは何でしょうか。低い人と思われるケースについてご紹介します。
教えてもらえないと、他責思考に陥る
自己解決能力が低い人の最大の特徴は、教えてもらう事が当たり前になっている事です。
- 仕事は上司が教えるもの
- マニュアルがなければ仕事は出来ない
- 分からない事はやりたくない
もちろん、仕事においてマニュアル化・仕組み化は重要です。また、上司がある程度は教えるべきです。
しかし、教えてもらうのが当たり前=クレクレ君の人に仕事を任せる事は出来ません。
特に上司が忙しい時は、教える時間より自分が行った方が早いと考え、せっかく新しい仕事を覚えられる機会を逃してしまいます。
-

自責思考と他責思考あなたはどっち?幸せになる正しい考え方を徹底解説
自分はダメだ。自分が悪いと思って思い詰めていませんか? 他責思考の人と付き合うことに疲れていませんか?あるいは人のせいばかりしていたりしませんか? 今回は、こんなポイントに当てはまる人に対して、幸せに ...
続きを見る
自己解決能力が高い人の場合
自己解決能力が高い人の場合は、マニュアルがなかったり、上司が教える余裕がない時は、自分で仮説を考え調べ、まずは行動に出して挑戦してみます。そして、上手くいかない場合は、再度調べて解決に近づこうとします。
結果、1つの物ごとにたいしてマニュアル通りに行うより、深く理解する事が出来、しっかり身に付ける事ができます。
問題の所在が分かっていない
何が問題なのか、なぜ問題なのか、どこが問題なのかと言う、いわゆる5W1Hで問題の所在が分からない人は、何を解決すべきかが分からない為、解決する事が出来ません。
特に仕事においては、一見何が問題ないか分からないけど出来ないという事もあります。
上司・同僚に質問する時に、「結局何が分からないの?」「もう少し具体的に教えてほしい」と指摘を良く受ける場合は、問題の所在が分かっていないと言えるでしょう。
これは、同僚・上司に教えてもらう時にも重要ですが、何が・なぜ・どこが問題なのか言語化する事が大切です。
基礎知識が欠如している
急に明日、「誰かを手術してください」と言われたら、どんなに調べても無理です。
なぜなら、基礎知識が欠如しすぎて、調べたらわかる程度の問題ではないからです。
数年かけて勉強し、経験を積んで出来るか出来ないかです。
手術は極端ですが、エクセルで票を作る業務でも、エクセルを触った事すら無ければ、調べるだけで数日かかってしまう事もあるでしょう。
基礎知識が欠如していると、自己解決はかなり難しくなります。
自己解決能力を高める為の考え方
問題を具体的に言語化・視覚化するクセを付ける
抽象的な問題とは「モテる方法」「稼ぐ方法」などです。
問題の範囲が大きすぎて解決方法にたどり着く事が難しくなります。
例えば、なぜモテないのでしょうか。もしかしたら、異性と話が続かない為、仲良くなれないのかもしれません。
そのような場合は、「異性と話を続ける方法」や、「女性・男性が好きな趣味・話題とは」など具体的な調べ方をするとより答えに近づく事が出来ます。
この時の言語化は、仮説で十分です。なぜできないのかを考えてみて、より抽象化できたらその問題に焦点を当てて調べたり解決方法を探ってみましょう。
もし、仮説に合う解決方法が見つかっても、上手くいかなかった場合は、仮説が悪いかもしれません。
仮説を考える→調べる→仮説を練り直す→調べるのように、繰り返し考えていく事で答えに近づく事が出来ます。
問題解決方法では、下記のページにてもっと詳しくご紹介してします。
-

【なぜなぜ分析とは?】結果を出す・改善するために、必須の分析法
仕事で、改善すべき点が分からない。 改善しているのにちっともよくならない。 そんな方に対して、自動車メーカーで有名なトヨタ車が提唱した「なぜなぜ分析」について解説していきます。 人の暮らしを改善して良 ...
続きを見る
普段から新たな事に挑戦するクセを付ける事
慣れている仕事は、詳しいはずで大抵の事は自己解決できるでしょう。
調べなければいけないような仕事の多くは、普段行っている業務以外の事が現れた時です。
仕事についても、趣味についても常に新たな事に挑戦すると、適応力が上がります。
新しい事は、分からない事ばかりです。必然的に自分で解決しなければならない事も増えていきます。
新しい事は、自己解決能力の訓練になります。
その為、新しい事と言っても仕事に関連する事でなくても、趣味でも何でも良いと思います。
常に新しい事に挑戦して、自分で考え調べ解決する力を養っていきましょう。
自分で考えて解決する事こそスキルアップに繋がると思う事
謎解きや、クイズで誰かに先に答えを言われてしまうと悔しいですよね。
同じように、どなたかに教えてもらうという事は、答えを先に言われてしまうような事だと思いましょう。
なるべく自分でやろうと思う事こそが、自己解決能力を高める為の重要な意識です。
さいごに
短期的に時間がない時は、上手に上司・同僚に聞く事は大切です。
しかし、自分でより多くの事を解決できるよう日頃から訓練していきましょう。